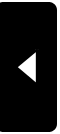京都の平岡八幡宮へ行きました!

今日は遠州鉄道のバンビツアーに参加して平岡八幡宮に行ってきました!
平岡八幡宮(ひらおかはちまんぐう)は、京都市右京区梅ヶ畑に位置する神社で、山城国最古の八幡宮として知られています。その歴史は平安時代初期の809年(大同4年)に遡り、弘法大師・空海が神護寺の鎮守社として、豊前国の宇佐八幡宮から勧請し、自ら描いた僧形八幡神像を御神体として祀ったと伝えられています。
本殿は室町時代に焼失しましたが、足利義満の奥方が高雄での紅葉狩りの際に荒廃した姿を見て心を痛めたことが再建のきっかけとなり、義満によって再建されました。現在の本殿は1826年(文政9年)に修復されたもので、京都市内に現存する数少ない切妻造の本殿の一つとして、2000年(平成12年)に京都市指定有形文化財に指定されています。
本殿の内陣天井には、1827年(文政10年)に画工・綾戸鐘次郎藤原之信によって描かれた44面の極彩色の花卉図があり、「花の天井」と呼ばれています。この「花の天井」は、毎年春と秋の特別拝観時に公開され、多くの参拝者を魅了しています。
境内には約200種の椿が植えられ、「椿の小径」として親しまれています。春には多種多様な椿の花が咲き誇り、訪れる人々の目を楽しませます。また、秋には紅葉の名所としても知られ、参道や舞殿周辺のタカオカエデやイチョウが美しく色づきます。
例祭は毎年10月上旬の日曜日に行われ、京都市指定無形民俗文化財である「三役相撲」が奉納されます。この神事では、地元の子供と大人が取り組み、神の加護を受けた子供が勝つという古くからの伝統が受け継がれています。
平岡八幡宮は、歴史的価値と自然美を兼ね備えた神社であり、四季折々の風景を楽しむことができます。特に春の椿と秋の紅葉の時期には、多くの参拝者が訪れ、その美しさに心を癒されています。

平岡八幡宮では、春と秋の特別拝観期間中に「大福茶(おおぶくちゃ)」が振る舞われます。この大福茶は、手作りの梅干し(福梅)と結び昆布が入ったお茶で、参拝者への接待として提供されています。
大福茶は、平安時代から伝わる縁起の良いお茶で、無病息災や長寿を祈願して飲まれてきました。平岡八幡宮で提供される大福茶も、参拝者の健康と幸せを願う心が込められています。
特別拝観の際には、宮司による説明とともにこの大福茶が提供され、訪れる人々にとって特別な体験となっています。
アンデス浜松